私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。
分類別: その他
「こんな夜更けにバナナかよ」
大泉洋主演「こんな夜更けにバナナかよ」
実話を基にした,筋ジストロフィー患者の生きざまを描いた物語。障害と闘いながらも自由奔放な(ワガママな?)鹿野靖明さんの自立生活とその周りに集まるボラの支援。入院も拒絶し,人工呼吸器も拒絶し,長く生きられないと言われた鹿野さんが,自分の運命と闘いながらも,命がけでワガママを言い続ける様が印象的。ワガママながらその生き方が周りの人々に「自分らしく,正直に」生きることを伝え,周りの人々も力を得ていく様が,「生きる」という深遠なテーマについて考えさせる作品に仕上がっていると思います。
重い障害を扱いながら,全編,重苦しい雰囲気は感じさせずに,微笑ましくも考えさせられる内容だったと感じました。
鹿野さんを演じた大泉さんの演技にも脱帽。
おすすめの一作です。

99.9%は仮説~思い込みで判断しないための発想法~
本日,金陵同窓会の定期総会・記念講演がありました。 主に,育徳館高校・中学のOBで構成される同窓会のようです。京築地域の名門ですね。
長崎出身のお前は縁もゆかりもないだろうと言われそうですが,私も毎年,協賛させていただいているのです。ご招待いただきましたので,記念講演だけですが,拝聴させていただきました。
講演者は,サイエンス作家の竹内薫氏。暗記型ではなく探求型の教育を手掛けているとのことでした。お題は,表題のとおり。
どんな話が飛び出すのか?と思いながら聞いていましたが,AI時代,これからヒトとAIがどのように歩んでいくか(仮説1:ターミネーターの世界。仮説2:鉄腕アトムの世界),という話から始まり,AIの特徴である自動化=最適化=思い込み?について実例・クイズをもとに検討し,柔軟で,手を変え品を変え工夫してできるよう,これからの教育を考えていくべきという内容で締めくくられていました。
大変に興味深く,私がまとめるのはおこがましいので,印象的だった部分だけ記載しますが,AIは「暗記」は得意だけど「常識」がなく,文脈や空気を読み取れないという話,AIはソーゾー力(想像力,創造力)が欠けているゾンビであるという話など,具体的な話を通して,「人間にしかできないこと」を考え,これからは,人工知能と人間のすみわけが大事になってくるということでした。
最後の質問では,自動運転の可能性についても議論がありました。自動運転においても,どこからどこまでがAIの領域で,どこから人の領域なのかのすみわけを考えることが大事とのことです。危険を察知してアラームを鳴らすところまでが機械の役割で,その後の判断・動作は人間の役割?それとも,機械の役割はもっと狭い?あまりに機械に頼って運転していると,人間の注意力が落ちていくため,どこまで任せるのか。実際に事故が生じたときの責任としても,機械のせい?ヒトのせい?…などなど,交通事故を取り扱う上でも,将来生じてくる論点の解決のヒントを得たような気がしました(あくまでとっかかりのレベルですが。)。
私の母校のうち,小学校は,既に建物がなくなってしまっています。連綿と同窓会が続いているのは素晴らしいことだと思います。貴重な機会をいただき,ありがとうございました。
「民事紛争ネットで解決」日経新聞記事の感想
令和元年7月7日(日)日経新聞の一面に,木になる記事がありました。先般行った支部交流会(裁判のIT化)にもかかわる内容ですので,取り上げます。
記事によると,政府は,離婚や交通事故といった民事紛争を,インターネット上で解決する仕組みづくりに乗り出すとのこと。記事の書きぶりからは,裁判のIT化の話をしているのか,裁判外の紛争解決のための仕組みの話も含むのか,判然としないところがありましたが,おそらく裁判のIT化の話をしているのでしょう。
ネット上で手続ができること自体は,悪いことではないと思いますが,情報管理の問題やシステム構築をどうするのかなど,課題は山積みのように思います。また,紛争を解決するという事柄の性質上,すべてネット上で行って当事者の納得のいく解決ができるのかも,疑問がないわけではありません。ある程度は,出頭・対面なども併用していくことは必要ではないかということも踏まえて,検討していただきたいと思います。
仕組みが出来上がることで,支部機能が縮小し,支部のハコがなくなり,ハコがなくなることでより司法が遠くなり,結局司法的な解決を選択しなくなるという悪循環も考えられますから,そのような問題はないかということも,支部の弁護士から声を上げていかないといけないかもしれませんね。
支部交流会 2019
令和元年6月29日(土)13:30~17:00,恒例となっています支部交流会が開催されました。九州弁護士会連合会の協議会が主催するもので,支部の弁護士が集まり,年1回,本庁にはない支部特有の問題について議論する交流会です。今年で10周年となり,感慨深いものがあります。私も,毎年,参加させていただいております。
今年の大きなテーマは,裁判のIT化と支部機能の縮小の懸念についてでした。そもそも,支部にはなかなか情報が伝わらないところがありますので,まずは情報共有のため,議論状況にお詳しい方々の報告をいただきました。これを踏まえ,支部に与える影響という観点で,活発な意見交換がなされております。最高裁は,IT化が支部の統廃合にただちにはつながらないというものの,IT化によって支部の事件数がさらに減っていけば,必然,統廃合の対象になるのではないかという懸念もあり,みなさん真剣に議論いただきました。大変有意義な意見交換ができたのではないかと思います。西南学院大学の民訴法の先生にもコメントいただくなどでき,大変貴重な機会となりました。
私は,ディスカッションの司会役を仰せつかっております。IT化に関して盛り上がったところで,関連する,支部の非常駐の問題を取り上げて議論いたしました。現在,支部では,平戸,壱岐,佐伯,竹田,山鹿,阿蘇,知覧,八女が,裁判官の常駐しない地域になっています。なかなか期日が入らずに進行が遅延するなどの問題があり,填補の裁判官の負担も重くなるため適切な審理ができるのかという懸念もあります。ここ最近では,中津の簡裁が,これまで常駐の裁判官がいたにもかかわらず,非常駐になってしまい,支部には裁判官がいても,簡裁にはいないという新たな(?)問題も生じているように思います。そのようななかで,運用の改善につき努めている支部もあり,これらを紹介いただくなどして,今後の運動のための参考とすることができました。
その他,現在,中央一極集中の傾向が強まり,過疎偏在地域はおろか,地方都市でも登録者が減っているような現状もあるようで,地方で志をもって活動する弁護士を採用するため,どのような努力・工夫があり得るかなどを議論しました。
毎年,支部の状況について勉強させていただき,最近では運営側にもかかわらせていただいておりますが,これからも,弁護士過疎偏在問題への対応を続けていき,そので学んだことを,豊前での弁護士活動にも還元していきたいと思います。
最高裁に告ぐ
法曹界の時の人,岡口基一裁判官の新刊レビュー第2弾です。
岡口裁判官は,書籍や情報発信など,法曹界のインフラの整備にもつとめている現役裁判官。ツイッターの投稿の件で,先般,分限裁判にかけられ,戒告処分になってしまいましたが,いまなお,今度は国会の訴追委員会との関係で,やり取りをしている最中です。
私も若手弁護士の1人だと思っていますが,若手で,岡口裁判官が出している,「要件事実マニュアル」「民事訴訟マニュアル」を持ってない人はいないのではないでしょうか,というぐらいに有名ですね(同書籍は「マニュアル」という名前からして依頼者の前では使いにくいですが,なかみは非常に整理されていて,最初に調べるものとしては最適の書籍です。)。
「最高裁に告ぐ」は,先日発売されたばかりですが,すでに増刷になっているとか。報道等で断片的に追いかけていた岡口裁判官の分限裁判につき,本人からの非常に詳細な経緯の説明や解説付きで,同事件の理解を深めるのに非常に役に立ちます。といっても,岡口裁判官の恨み節が展開されているわけではなく,岡口裁判官が,法的な視点で問題と思われることを深掘りした上,さらに,近時の最高裁の動向にまで視野を広げ,広く司法の在り方について問題提起しているものといえると思います。
さて,本作で直接取り上げられているのは,とある裁判について,興味深い論点があるということで,これを140字の字数制限があるツイッターで要約した内容を示したところ,この内容の発信が裁判官の懲戒事由にあたるとして裁判にかけられたものです。広島大学の法科大学院で,公法系に力を入れて勉強していましたが,試験によく出るものの,学説と判例を何度読み比べても,当初うまく腑に落ちなかったのが,表現の自由の分野です(他の分野でもそうなんでしょうが,憲法では頻出論点の為,接する機会が多かっただけかもしれませんが。)。報道の自由は,表現の自由のなかでも,特別な意味を与えられているように感じていますが,裁判官の表現の自由についても,広く表現の自由の問題というよりは,固有の問題のようにとらえて考えていました。従来から,裁判官を含む公務員について,中立・公正といっただけでなく,それ「らしさ」まで厳格に求め,結果として,裁判官の表現の自由についても,通常よりは制約が許容されてしまうのかな,どうなのかな,寺西判事補事件から今に至るまでで変化はあったのかな(最高裁でも,しばしば「時の経過」論というものが展開されます。)といった種々の論点につき,整理ができないままでいたところです。この点,今回の決定では,何らか重要な判断が示されるのではなかろうかと注目して経過を見守っていました。ところが,実際は,表現の自由の話には,わずか数行しか触れず,実質何らの説明もしていません。岡口裁判官でなくても,肩透かしをくらったような印象を持ってしまうのではないでしょうか。そのような審理・判断の問題点について,改めて考えることができてよかったと思います。ロースクールでも,表現の自由を学び考える,格好の材料になりそうですね。
読みやすく,それでいて内容も濃く,一気に読み通すことができました。
何といっても,本書の最大の見どころは,度々,ロースクール時代の恩師,新井誠先生のご意見が紹介されていたところです。みなさま,どうぞご注目ください。
例によって,本書も,弊所の相談室に備置することになります。ご興味のある方は,ぜひともお声掛けください。
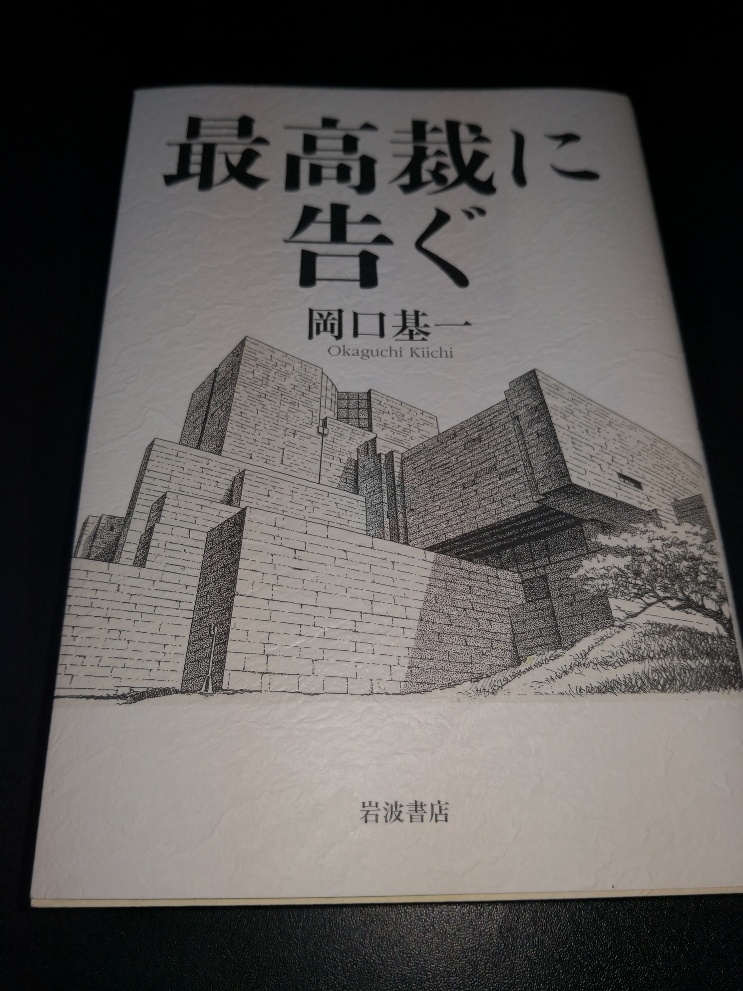
武蔵屋総本店/うす皮饅頭
もう2年以上前になりますが,弊所の開所セレモニーを催した際,お出ししたもののなかにおいて,ダントツで人気があったのが,「うす皮饅頭」でした。名前のとおり,ボリュームたっぷりのあんこを,うすーい皮で覆ったスイーツです。
武蔵屋総本店にて購入できます。たまたま,本日,買い物する機会がありましたので,ご紹介します。
どら焼き,桜餅などなど和菓子もたくさんですが,甘味処では,絶品パフェなども味わえるようです。今度食べてみたいと思っています(本日は終わってしまっていました…)。
おすすめは,冒頭にも示したうす皮饅頭。単品で購入すれば80円程度からでお手頃ですし,お土産にしても喜ばれると思います。私も,弊所までいらしていただいた方々には,たびたび,お土産としてお出ししています。ご賞味あれ。


イチケイのカラス
「イチケイのカラス」。漫画ですが,なかなか面白いです。特に,法曹関係者の方には,ウケる内容だと思います。
最近は,弁護士にフォーカスしたドラマが多いですが,一昔前には,検察官のドラマがはやりました。キムタクの「HERO」は典型ですね。私は,検事が,「被害者の声を届けられるのは検察官だけだ」という趣旨のセリフを述べていたのが,鮮烈に記憶に残っています。そうか,検事は,そのような使命感をもって,尊い仕事をしているのだな,と。
一方,日本は,諸外国のように,裁判官が支配する法廷といったような感じの裁判ではなく,割と淡々と進んでいくようなところがあるためか,裁判官を題材にしたドラマや漫画というのは少ないように思います(有名な「家裁の人」くらいでしょうか。)。
その意味では,異色のヒューマン・ドラマなのかもしれません。「イチケイ」というのは,「第一刑事部」のこと。裁判所の,刑事裁判を担当する部署のことを指します。そこでは,頭の固い中堅から,個性的な判事まで,さまざまなメンツが活躍する裁判劇が展開されます。先日発売された第3巻は,冒頭はクレプトマニア(窃盗症)に関する審理の話,後半は裁判員裁判の話が描かれていました。裁判員裁判とか,結構細かいところもリアルに描いていますよ。裁判員の選任手続(理由なし不選任の話なども出てきます。)とか,証人尋問で用いる機器類の描写とかも含めてですね。
さすが,櫻井先生に取材したり,さまざまな参考文献を参照しているだけありますね。
地味といえば地味な作品かもしれませんが,噛めば噛むほど味わい深いするめのような作品だと思います。東京地裁内の至誠堂書店では,法曹三者が買っていくものだそうで,法曹三者のお墨付きの作品です。
幣所の待合室に備え付けておきますので,興味がある方はぜひご覧ください。
жжж追記жжж
単行本派の私は情報をキャッチできてなかったですが,打ち切られるみたいです。残念。
福岡市が地方最強の都市になった理由
まちづくりのお勉強第2弾です。木下斉「福岡市が地方最強の都市になった理由」を読みました。
福岡市は,一級河川もなく水源が確保できない点を直視して,当時他の地域が製造業/工業地域の展開に力を注ぐ中,前へならいはせず,いちはやく第三次産業(サービス業)に注力し,地域を発展させてきたということでした。横並びの政策ではなく,民間主導で,自らの弱みを強みに変え,地域の特性に応じ,適切な産業の展開をしていくという構図は,確かに,理想的なまちづくりの在り方なのかもしれないと思いました。
福岡市とはいえ,行政主体で失敗したという博多リバレインの例など,成功事例ばかりではなくバランスよく検討している印象でした。
利益だけよその地域にもっていかれないよう,支社機能ではなく本社機能をもってこれるまちでないといけないなど,示唆に富むお話もたくさん。身近な地域,誰でも知っている都市のことだけに,リアリティもあって,わかりやすいです。
豊前市にもこうした地政学を活かしていきたいところですが…
私も,どうしていけばいいのか,考えていきます。
TOTO/工場リモデルフェア in 中津
平成31年3月9日,@TOTOサニテクノ中津工場,「工場リモデルフェア」イベントに参加してきました。
駐車場にはたくさんの車が。会場に向かうと,やはりたくさんの人がにぎわっていました。TOTO製品の紹介スペースだけでなく,屋外にはトヨタ・ダイハツの車の展示会や,消防車やパトカーの展示・試乗会などがあったり,ふれあい動物園が模様されていたりと,さまざまなイベントが行われていました。飲食コーナーも子ども連れのご家族を中心に,たくさんの人でごった返しておりました。中津らしく,洞門バーガーをいただきました(注;地元産の新鮮な野菜と耶馬渓の黒豚のパテを竹炭入りバンズではさんだ中津のご当地バーガー。)。
さて,メインイベントは,平成29年5月に完成した工場で,トイレの製造工程を実際に見学する,工場見学です。どんな材料でつくられるか?実際に見せていただき,どうやって形作るか?どうやって焼くのか?などなど,実際に見て,説明を受けながら,見学をすることができました、なかでも,形作ったトイレを焼く工程では,長ーい窯の中を実際にのぞき込んで,十数時間もゆっくり進めながら焼いていくという様子の一部を見学しました。何時間もかけないと,表面を焼くことはできるが,しっかりなかまで熱が通らず,もろくなってしまうなどという問題意識があるからだそうです。勉強になりました。
工場見学は,普段は,平日の9時~12時,13時15分~16時の間で,要予約,90分間の見学を可能だということでした。今回は,40分の見学でしたが,普段はまた違うのでしょうかね。もう1度見てみたいなと思いました。
私は,いろいろな工場の見学をしてまわるのが好きです。自分が経験し得ない世界ですので,それらを見て,そこがどんな企業なのか,どんなこだわりをもっているのかなど,見て,知って,自分の世界を広げていきたいと思いますし,日常自分たちが使っている製品のことをもっとよく知れば,単に「使う」にとどまらない,深く楽しく広がりのある毎日を送っていけるのではないかと思うからです。
中津には,今回のTOTOをはじめ,ダイハツの工場があったりなど,産業の街だけあって,いろいろな工場があるようです。また,いろいろと見て回りたいものですね。
工場見学【お問合せ】
TOTOサニテクノ㈱中津工場 総務課 TEL:0979-32-1111 担当:島元 URL:http://totosanitechno.jp/
ひなまつり in 中津
本日はひなまつり。
残念ながら,天気は小雨でしたが,中津城・城下街は,ひなまつりムード一色です。
中津城では,市民が扮してひなまつりを体当たりで実演。なかなかの迫力。
城下街では,南部まちなみ交流館にて,きらびやかなひな人形展が。琴の実演などもあり,いろいろと楽しむことができました。
中津市でも,さまざまなイベントが行われています。商売の街として,今もなお栄えています。ぜひ1度足をお運びください。
【中津城】

【南部まちなみ交流館】



